

その2
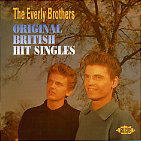 |
Original British Hit Singles/The Everly Brothers アルバム・タイトルの通りエヴァリーズのイギリス発売のヒット・シングルを集めたコンピ盤で1994年リリース。 全22曲収録でエヴァリーズとは最も縁があったと思われる“ブードロー・ブライアント”の作品が大半を占める。 ブードロー・ブライアントといえばチェットの「チャップリン・イン・ニュー・シューズ」の作者としてチェット・ファンにも お馴染みだが、このアルバムでもその美しいメロディが充分に楽しめる。 さて、肝心のチェットだが、お馴染みのロックン・ロール曲「ビーバップ・ア・ルーラ」で、“いつものチェット”と違う 雰囲気の演奏を楽しめる。エヴァリーズとは縁の深かったチェットだからこのアルバムの他曲でも参加はあるのかも しれないが、私の耳には「これがチェット」という演奏はないように思われる。 |
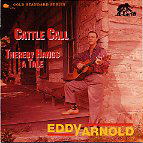 |
Cattle Call、Thereby Hangs A Tale/Eddy Arnold ドイツのベア・ファミリーからリリースされてるエディ・アーノルドの2in1仕様のCD。 ベア・ファミリーのCDに良くあるベスト・アルバム的なものではなく、1959年の「Thereby Hangs A Tale」と1963年の 「Cattle Call」を1枚のCDにまとめたものだ。 両作品共にチェットのプロデュースであり、「Thereby Hangs〜」では演奏にも参加。 とはいうもののチェット・ファンは多くを期待してはいけない。 曲の多くはアコースティック・サウンドでチェットらしいプレイは殆ど聞けないからだ。 ただ珍しいのは何曲かでバンジョーを演奏しており、僅かながらソロも聞ける。 チェットのそれらしい演奏が聞けないという意味では熱心なチェット・ファンには無意味なアルバムかもしれないが、 歌とアコースティックなバック・サウンドは実に美しく枯れており、古いカントリーの良さを満喫できる。 |
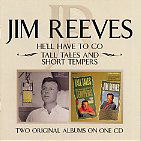 |
He'll Have To Go:Tall Tales and Short Tempers/Jim Reeves ジム・リーブスの「He'll Have To Go」と「Tall Tales and Short Tempers」を2in1にしたコンピ盤、という触れ込みの CDだが、「He'll have To Go」に関しては、付属のリーフレットにある当時のジャケット写真に書かれてる曲目とこの CDの収録曲が一致しない。 どうも良く分からない部分があるが、何曲かでチェットの美しい演奏が聞ける。 もっとも素晴らしいのがチェット自身が「CHET」(1967)で取り上げてるウディ・ガスリー作の「Oklahoma Hills」だ。 もともと美しい曲で「CHET」でもいろいろなテクニック・パターンを駆使して見事な演奏をしていたが、ここで聞ける ジム・リーブスの歌伴も素晴らしい。 はっきりチェットと確認できる演奏はほんの数曲だが、ジム・リーブスの素晴らしい歌声に絡むチェットのギターは また別の魅力があって私はとても気に入っている。 |
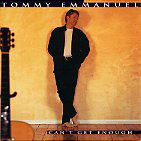 |
Can't Get Enough/Tommy Emmanuel 1996年リリース作品。 ラリー・カールトン、ロベン・フォードをゲストに迎えたギター・アルバムの佳作。 12曲目の「How Many Sleeps?」でチェット・アトキンスが共演してる。 “弾き過ぎ”としてトミーのプレイを好まない人もいるが、このアルバム、全体的に静かなムードが漂い、チェットとの 共演曲もチェットの晩年の作品に通ずるような“滋味”傾向の強い曲になっている。 こういうスタイルは全盛期のチェットとは全く異なるので好みは別れると思うが、これは晩年期のチェット作品を象徴 するような味わいで、リラックス・ムードの優しさに満ちている。 |
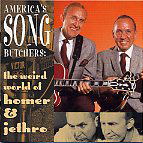 |
America's Song Butchers:The Weird World of Homer & Jethro 1997年にリリースされたコンピ盤。 全20曲のうち11曲でチェットがエレキ・ギターで参加してる。 殆どの曲が1940年代後期から1950年代半ば頃までの録音で、ホーマー&ジェスロといえば私はインストの印象が 強いのだが、本作は歌物で構成されている。後にチェットが好んで演奏するようになった「ミスター・サンドマン」が 収録されてるのが興味深いし、ソロは弾いていないがビートルズの「抱きしめたい」をオリジナルの雰囲気を壊す ことなく演奏してるのも何だかとても面白い。 またジョー・スタッフォードが歌って大ヒットした「ユー・ビロング・トゥー・ミー」がチェットの伴奏で聞けるのも得した 気分だ。余談だけどこの曲の作者はあの「テネシー・ワルツ」の作者でもあり、アメリカに2大名曲を残した事になる。 |
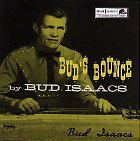 |
Bud's Bounce/Bud Isaacs 今年ドイツのベアファミリーからリリースされたばかりのホヤホヤのCDだ。 ペダル・スティール・プレイヤーの第一人者、バッド・アイザックスの演奏を集めたものだが、プロデューサーをチェット が担当して演奏面での参加も多い、チェット・ファンには有り難いアルバムだ。 全25曲収録のうち17曲でチェットが参加してるが、全般的にチェットは「チェットらしさ」を排除してるように聞こえ、しかも その演奏はやっぱり素晴らしいのだ。流石のチェットである。 すべての曲でソロが聞ける訳ではないけれど、素晴らしいソロが聞ける曲もありファンは必携だ。 ペダル・スティール奏者が好んでレパートリーに加える「Bud's Bounce」はこの人のオリジナルで、私はバック・オウエン スの「I Don't Care」というアルバムでこの曲を知ったが、このアルバムには2テイク収録されてるのが嬉しい。 ベア・ファミリー恒例のブックレットも充実の43ページだ。 |
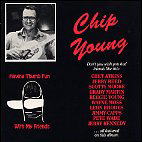 |
Chip Young/Having Thumb Fun With My Friends アルバム・タイトルが示す通り、実力者チップ・ヤングが自らの交友関係?ギタリストを招いて制作した好ましいギター・ アルバムだ。 ゲストはジェリー・リード、スコッティ・ムーア、グラディ・マーチン、レジー・ヤング、ウエイン・モス、レオン・ローズ、そし て我らがチェット・アトキンスで、良くもまあ凄いメンバーを集めたものだ。 ここ何年かナッシュビルのミュージシャンが集まってカントリー系のインスト・アルバムを出したりしてるが、そういった 若いミュージシャンとの差を歴然と感じさせる仕上がりだ。 特に私が注目したのがレジー・ヤングとレオン・ローズの参加だ。 レジー・ヤングはあのアクの強い音が影を潜め、とてもナチュラルな素晴らしい音を聞かせているし、こういったセッショ ンには殆ど顔を見せないレオン・ローズの参加は、私にとっては身震いものの感動なのだ。 そうそう、チェットは「Oh! By Jingo」で素晴らしいプレイを聞かせてくれます。ギター・ファン必携のアルバムだ。 |
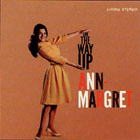 |
Ann Margret/On The Way Up 1961年リリースの作品。 ナッシュビル録音の強引に言えばカントリー・アルバムと言えるのか。 まあしかし収録曲を見れば「Fever」「Heartbreak Hotel」「Moon River」なんて曲が並んでいるから、オーソドックスなポッ プ・アルバムをナッシュビルで録音したというだけのようだ。 チェットはプロデュース、及び演奏にも参加。とはいえそんなに目立ったプレイをしているワケではない。 ライナーによると「Oh Lonesome Me」でソロを弾いてるとあるが、“それらしくない”プレイで「本当か?」と疑問も持ってし まう。しかしチェットの存在を抜きにしても個人的には好きなアルバムで、あの時代のガールポップの雰囲気が良い。 「Moon River」や「Could It Be?」のドリーミーな雰囲気、そしてヘレン・カーターの「What am I Supposed to Do」で聞 かせる間奏部の語りなどが時代を感じさせて良い。 |
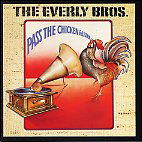 |
The Everly Brothers/Pass The Chicken & Listen エヴァリーズ、1972年のナッシュビル録音作品。 チェットはプロデュース&プレイヤーとしても参加。 本来の?と言っては語弊があるかもしれないが、上記のアン・マーグレット作品に聞けるようなヨソ行きの感じはなく、 ナチュラルに音楽にとけ込んでいる。参加ギタリストはポール・ヤンデルをはじめ何人か参加しているので、すべて チェットの演奏というワケではないが、そこかしこでそれらしいチェットの演奏が聞ける。 中でも3曲目「Woman Don't You Try to Tie Me Down」では、エヴァリーズはチェットの名前をコールして、それから チェットのソロが始まり他のプレイヤーにリレーされる構成で楽しい。 当然エヴァリーの歌を聞くアルバムではあるが、ギターの演奏もそれぞれに楽しくて、ギター・アルバム的側面も併せ 持つ。余談だがペダル・スティールはRCAセッションでしばしば登場するウェルドン・ミリックだ。 |
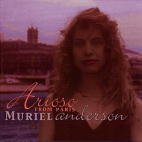 |
Muriel Anderson/Arioso from Paris メリエル・アンダーソン、1992年のパリ録音。 チェットのフォロワー、或いはフィンガー・ピッカー系という括りで考えれば“女性”というのは非常に珍しいが、クラシック ばかりでなくポップなフィールドに女性ギタリストが進出するのは大いに好ましい。 この作品、ジャケット背面に記載された「this instrumental guitar music was inspired by many cultures and many places, including the beautiful French countryside」の言葉通りの美しい世界が詰められている。 チェットとの共演は名曲「To Be or not To B」だが、チェットの演奏は遠慮がちだ。しかしこれはこの曲に限らずこのアル バム全体を支配してるゆったりした安堵感に歩調をあわせた演奏と言える。 その他、琴の音を模したと思われる「荒城の月」や、かつてチェットも演奏したダイア・ストレイツの「Why Worry」などが美 しい。全体の印象としてはチェットの晩年作品を思わせる滋味感覚溢れる好盤だ。 |
| チェット・ワークス1へ |