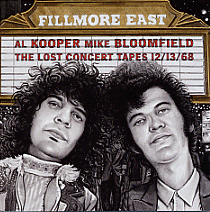
02 One Way Out
03 Mike Bloomfield's Introduction
of Johnny Winter
04 It's My Own Fault
05 59Th Street Bridge Song
06 (Please) Tell Me Partner
07 That's All Right Mama
08 Together Till The End of Time
09 Don't Throw Your Love On Me So Strong
10 Seazon Of The Witch
MHCP 2009
2003.06.04発売
税込み1.785円
(何と言っても
この値段が嬉しいのだ)