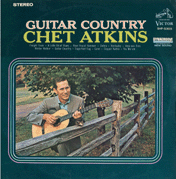Chet Atkins
Guitar Country
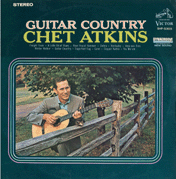 |
01 Freight Train
02 A Little Bit Of Blues
03 Nine Pound Hammer
04 Dobro
05 Kentucky
06 Vaya Con Dios
07 Winter Walkin'
08 Guitar Country
09 Sugarfoot Rag
10 Gone
11 Copper Kettle
12 Yes Ma'am |
オリジナル1964年
LSP2783
|
CD復刻
2001年
BMG
COL-2819
DRC12985
(1965年発表のMore of That
Guitar Country と2in1作品) |
1964年にRCAから発売されたチェットの力が漲る1枚。
個人的にも好きなアルバムで、チェットのルーツと言ってもいいカントリーをベースにした演奏が私のようなファンには嬉しい。
だからと言ってコテコテのカントリー・カバー集になっているワケではなくて、チェット流カントリー・ギター・ワールドの世界が広がる演奏だ。
この翌年に「もっとカントリーギターを」というファンの声に後押しされたのかどうか定かではないが、本作と同様のコンセプトを持った「More
of That Guitar Country」という文字通りのアルバムがリリースされるが、どうも私は1964年作の本作の方が好きだ。
チェットが元々カントリー・サーキットで活躍していたギタリストだという事は今更説明の必要もないが、キャリアを積んでいくに従ってカントリーという狭い枠にとらわれる事なく、よりトータルなギタリストとしての道を歩んだ事でファンの好みも二分されるようだ。
チェットは好きだがカントリー・ミュージックは聞かないという人は珍しくないし、逆にカントリー・エッセンスの感じられないチェットは聞かないなど人の好みは実に様々だ。
結果的にチェットは実に長きにわたってトップ・ギタリストとしての地位を維持した稀有な存在であったが、いかにチェットといえども駄作はあるし、プレイヤーとして波もあったと思う。しかし、特に50年代から60年代にかけてはチェットのもっともチェットらしい演奏が聞ける時期で、本作もそんな只中で製作されたものだ。
本作に収録されただいたいの曲は1963年10月に録音されており、(関係ないが)日本では翌年に控えたオリンピック開催に備えて準備に追われていた頃に録音されたものだ。
アルバムのトップを飾るのはメロディが美しくチェット・ファンには馴染みが深い「フレイト・トレイン」だ。
美しいメロディを持った私の好きな1曲だが、個人的な好みで言えばライブ・アルバム「The
Best of Chet On The Road LIVE」に収録されている「チャタヌガー・トレイン」とメドレーで演奏されているテイクが好きなのだが、何しろこのテイクは演奏時間が短くて欲求不満が残ってしまうという難点があるのだ。
アメリカは車社会という印象が我々には強いが、何故か音楽の世界には鉄道を題材にした物も多く、「フレイト・トレイン」には同名・他曲も存在していて時々間違えてしまう事もあるので注意が必要なのだ。
2曲目ではブルースを演奏している。
チェットはしばしばブルースも演奏するが、それは当然本家ブルース・アーティストが演奏するようなチョーキングとヴィブラートに彩られた演奏ではない。
・・・が、しかし、ここで聞けるチェット流ブルースは何時になくハードな味わいを持っているような気がするのだ。
ドイツのベア・ファミリーから出されている「Galloping
Guitar-The Early Years-」の1枚目でトップを飾っているのはそのものズバリなタイトルが付けられた「Guitar
Blues」(1946)という曲だが、これなどを聞くとチェットがこの後ブルースの道に進んだとしても決して不思議とは思われないような演奏を繰り広げているが、一見相反するかに見えるブルースとカントリーをとても起用に弾きこなしているのは驚異だ。
とは言ってもやはりこのブルースがチェット流の色彩に彩られているのは疑いようもなく、巧みな音使いはこの頃既に他を凌駕しているように思われる。
ついでながら「Guitar Blues」にはあのロイ・ランハムも参加している。
他にはチェットにとっては師でもあるマール・トラヴィス作品の「Nine
Pound Hammer」や、ハンク・ガーランドの「Sugarfoot
Rag」など多彩な曲を聞かせる。
中でも注目すべきは愛弟子、ジェリー・リードの作品を3曲も演奏している点だ。
チェットが他のギタリストと共演しているアルバムは数多いが、その中でも私個人としてはジェリー・リードとの共演がいちばん好きなのだ。
そしてこのアルバムに収録されている「Winter
Walkin'」はジェリーとの共演作品の中では最も好きな1曲になっている。
ギタリスト・・・・いや音楽家を顔で判断してはいけないが、こんなに美しいメロディがあのアメリカの田舎者然とした顔付きのジェリーから生み出されたのが、失礼な言いがかりとは承知しつつ不思議に感じてしまうのだ。
技術的にはそれほど難解な事をやっているとは思われないが、実はこういう雰囲気こそチェットでなくては出せない味だと思うのだ。
タイトル・チューンになっている「Guitar Country」ではチェット・ファミリーとしてしばしば顔を出すアニタ・カー・シンガーズが参加している。
これは私の個人的な想いなのだが、アニタ・カー・シンガーズを聞いていて良く思うのは、チェットのギターをヴォーカルに置き換えたらアニタ・カー・シンガーズに非常に近いものになるのではないかという事だ。
もちろんチェットのギターをそのままヴォーカルに置き換えるという事ではなくて、音楽の捉え方が似ているとでも言ったら良いのだろうか。
このコーナーの「Play Back Home Hymns」のところでも触れているのだが、特にこの作品とアニタ・カー・シンガーズのヘンリー・マンシーニ作品集である「We
Dig Mancini」というアルバムに大いなる共通点があるような気がしてならない。
「We Dig Mancini」のプロデュースがチェットである事を考えればチェットの音楽に似ていて当然という見方も出来るのだが、それにしても全編に漂うチェット・カラーはタダ者ではないと思っている。
「We Dig Mancini」は今のところ未CD化のようだが、チェット・ファンには聞いて欲しい作品だ。
尚、冒頭に掲げたアルバム・ジャケットの写真はアナログ盤のものを使用したが、現在この作品は本作の翌年に発表された「More
of That Guitar Country」というアルバムと2in1で復刻されているので入手は容易だ。