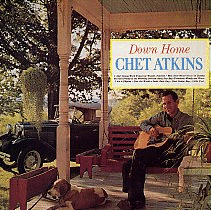
02 I'm A Pilgrim
03 Trambone
04 Steel Guitar Rag
05 Little Feet
06 Blue Steel Blues
07 Windy And Warm
08 I Ain't Gonna Work Tomorrow
09 Never On Sunday
10 The Girl Friend Of The Whirling Devish
11 Give The World A Smile
12 Tuxedo Junction
OW35123
現在このCDは「The Most Popular Guitar」とのカップリング
で2in1仕様で入手可能。
左記のジャケット写真もCDから使用しました。